
では、さっそく問題です!
- 金融リテラシー初心者でも楽しく学べる!お金の基礎知識クイズ
- 第11問 ペイオフ(預金保護制度)で保護される上限はどれ?
- 第12問 iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金に対する税制優遇として正しいのは?
- 第13問 インデックスファンドの特徴として正しいのは?
- 第14問 あなたが1ドル=100円のときに1,000ドルの外貨預金をしました。その後、円安が進んで1ドル=120円になったとき、円に戻すとどうなるでしょうか?
- 第15問 クレジットカードの「分割払い」の注意点として正しいのは?
- 第16問 「医療費控除」に該当するのはどれ?
- 第17問 定期預金を中途解約すると一般的にどうなる?
- 第18問 新NISAの「つみたて投資枠」で購入できる商品は?
- ✅ 積立投資枠で選べる投資信託(まとめ)
- 第19問 家計の「固定費」の例として最も適切なのは?
- 第20問 「高額療養費制度」について正しい説明はどれ?
- ✅ 採点の目安
- あなたにお薦めな記事
金融リテラシー初心者でも楽しく学べる!お金の基礎知識クイズ
第11問 ペイオフ(預金保護制度)で保護される上限はどれ?
- A. 元本1,000万円とその利息まで
- B. 元本500万円のみ
- C. 金額の制限はない
👉 答えを見る
正解:A(元本1,000万円とその利息まで)
銀行が破綻しても、預金は元本1,000万円+その利息まで保護されます。

ペイオフ制度、銀行が破綻しても 元本1,000万円とその利息 までは保証されます。
それを超える部分は保証されないため、資産を複数の銀行に分散するのがリスク管理の基本です。
第12問 iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金に対する税制優遇として正しいのは?
- A. 掛金は全額が所得控除の対象
- B. 掛金の半分だけが所得控除
- C. 掛金は所得控除の対象外
👉 答えを見る
正解:A(掛金は全額が所得控除の対象)
iDeCoの掛金は全額が所得控除となり、課税所得を小さくできます。

iDeCoの掛金は 全額が所得控除の対象 。簡単に言うと、支払う税金が安くなる
たとえば年収500万円で掛金を年間27.6万円にすると、課税所得がその分減るため住民税・所得税の負担が軽くなるよ!
第13問 インデックスファンドの特徴として正しいのは?
- A. 市場平均に連動する運用を目指す
- B. 毎年必ずプラスになる
- C. 高配当が保証されている
👉 答えを見る
正解:A(市場平均に連動する運用を目指す)
インデックスファンドは指数(市場平均)に連動するよう運用され、低コストが特徴です。

インデックスファンドは 市場平均に連動 する運用を目指す。マラソンで例えると、無名の優勝者を当てるのではなく、その大会の平均タイムで走れる人だけを厳選した選手選びだな!
「TOPIX」「日経平均」「S&P500」などの指数に連動し、個別銘柄選びをせずに広く分散できるのが特徴です。
第14問 あなたが1ドル=100円のときに1,000ドルの外貨預金をしました。その後、円安が進んで1ドル=120円になったとき、円に戻すとどうなるでしょうか?
その後、円安が進んで1ドル=120円になったとき、円に戻すとどうなるでしょうか?
- A. 円での受取額が増えやすい
- B. 円での受取額が減りやすい
- C. 為替の影響は受けない
👉 答えを見る
正解:A(円での受取額が増えやすい)
円安時は外貨→円に戻すと円換算額が増えやすい(為替差がプラスに働く)です。

これ、初見さんはごちゃごちゃになるので説明を詳しくします。
1ドル=100円のときは、1ドルを買うのに100円が必要です。
ところが円の価値が下がって、ドルの価値が上がったとしたら、1ドル=120円を出さないと1ドルと交換できなくなる。
つまり、円安のときに外貨を円に戻すと、円よりドルの方が価値が上がったので100円だった1ドルを、高くなったドル(1ドル=120円)と交換できる。
第15問 クレジットカードの「分割払い」の注意点として正しいのは?
- A. 回数によっては手数料(利息)がかかる
- B. いつでも無金利で利用できる
- C. 分割払いはポイントが一切付かない
👉 答えを見る
正解:A(回数によっては手数料がかかる)
分割払いは回数に応じて手数料(利息)が発生。総支払額が増える点に注意。

分割払いは一見便利ですが、 回数に応じて手数料(利息)が発生 します。
例えば10万円を12回払いにすると、数千円の手数料が加算され、総支払額が膨らみます。
緊急時以外は分割での支払いは極力控えようね!
第16問 「医療費控除」に該当するのはどれ?
- A. 一定額以上の自己負担医療費があると確定申告で控除を受けられる
- B. 支払った保険料の全額が控除になる
- C. 市販の化粧品代は広く控除対象
👉 答えを見る
正解:A(一定額以上の自己負担医療費で控除)
1年の自己負担医療費が一定額を超えると、確定申告で所得控除を受けられます。

医療費控除は、1年間に支払った自己負担医療費が 一定額(10万円または所得の5%)を超えると対象 になります。
医療機関の領収書や薬のレシートを保管しておくと申告に使えます。
🩺医療費控除の対象になる/ならない支出一覧
| 区分 | 主な例 | 医療費控除の対象? |
|---|---|---|
| 医師・歯科医師による診療費 | 診察料、治療費、入院費 | ✅ 対象 |
| 治療のための医薬品 | 処方薬、ドラッグストアで買った風邪薬や鎮痛薬(治療目的) | ✅ 対象 |
| 治療・療養に必要な費用 | 通院のための公共交通機関の交通費(電車・バス代) | ✅ 対象 |
| 出産に関する費用 | 出産費用、妊婦健診、分娩のための入院費、助産師による介助 | ✅ 対象 |
| 歯科治療 | 治療目的の虫歯治療、歯科矯正(子どもの噛み合わせ矯正など) | ✅ 対象 |
| 入院時の付帯費用 | 部屋代(差額ベッド代を除く)、食事代(治療食) | ✅ 対象 |
| 治療用装具 | 医師が治療のために指示した義手・義足・補聴器・義歯など | ✅ 対象 |
| 医師の指示で購入する眼鏡・補聴器 | 視力回復のためのメガネ(弱視治療用)、補聴器 | ✅ 対象 |
| マッサージ・整体 | 医師の治療としての指示があるもの(治療目的に限る) | ✅ 条件付き対象 |
| 美容目的の費用 | 美容整形、ホワイトニング | ❌ 対象外 |
| 健康増進のための費用 | 健康診断(治療に至らない場合)、予防接種 | ❌ 原則対象外(ただし要再検査で治療につながった場合はOK) |
| サプリメント・栄養ドリンク | 健康維持・美容目的 | ❌ 対象外 |
| 入院中の日用品費 | パジャマ、洗面用具など | ❌ 対象外 |
| 差額ベッド代 | 個室を希望した場合の追加料金 | ❌ 対象外 |
| 自家用車のガソリン代 | 通院に車を使った場合のガソリン代 | ❌ 対象外(公共交通機関のみ対象) |
第17問 定期預金を中途解約すると一般的にどうなる?
- A. 適用金利が下がり、受け取る利息が少なくなる
- B. 金利・利息は契約通りで変わらない
- C. 元本が減ることが多い
👉 答えを見る
正解:A(適用金利が下がる)
中途解約すると約定通りの金利は適用されず、受取利息が小さくなります。

定期預金は「〇年預ける」と約束した代わりに、普通預金より高い金利がつきます。
ところが途中で解約すると、その約束が守られないため、金利は普通預金並みに下がってしまい、利息はほとんど受け取れません。
元本(預けたお金)が減ることはありませんが、**「せっかくの利息が大きく減る」**のが中途解約のデメリットです。
第18問 新NISAの「つみたて投資枠」で購入できる商品は?
- A. 金融庁が定める基準を満たした投資信託など
- B. どんな投資信託でも自由に買える
- C. 個別株のみ購入できる
👉 答えを見る
正解:A(基準を満たした投資信託など)
つみたて投資枠は長期・積立・分散に適した商品(金融庁基準)に限定。
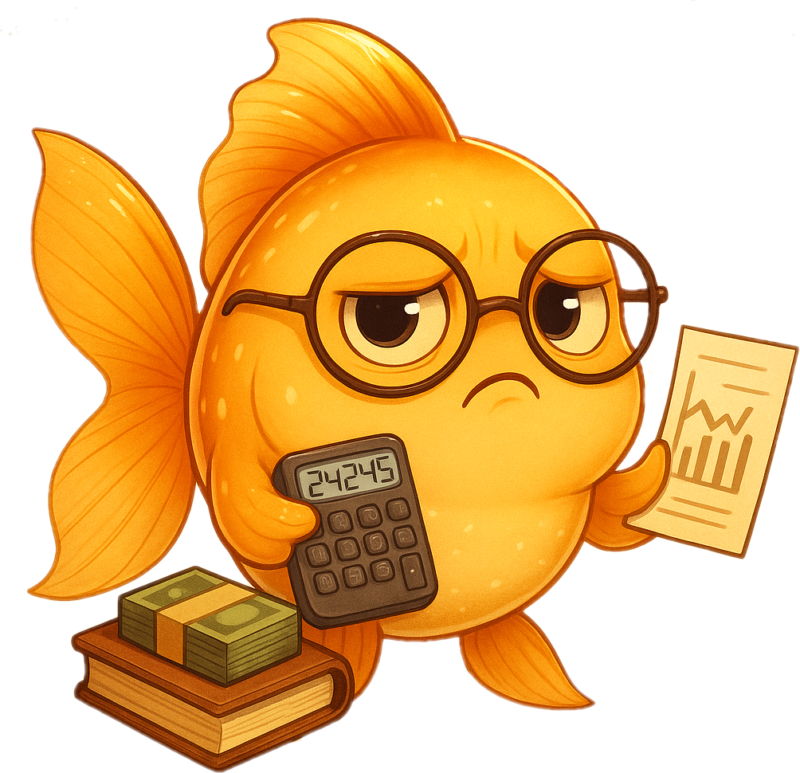
✅ 積立投資枠で選べる投資信託(まとめ)
積立投資枠では、金融庁が定める基準を満たした「長期・積立・分散に適した投資信託」だけが選べます。ようは国が認めた良い商品ですね
ポイントは以下の通りです👇
- 販売手数料はゼロ(ノーロード)、信託報酬も低コスト
- インデックスファンド中心で、長期運用向き
- 分配金は再投資型(毎月分配型は対象外)
- 運用実績や規模が安定している(一定の純資産残高・運用年数)
- 短期運用やデリバティブを多用する商品は対象外
第19問 家計の「固定費」の例として最も適切なのは?
- A. 家賃や通信費など毎月ほぼ一定の支出
- B. 食費など日によって変動が大きい支出
- C. 旅行費など不定期の支出
👉 答えを見る
正解:A(家賃や通信費など毎月一定の支出)
固定費=毎月ほぼ一定の支出。見直しで家計の改善効果が出やすい部分です。

固定費とは、毎月決まって発生する支出で、例として 家賃・保険料・通信費 があるよん。
ちなみに食費は変動費ね!👉 食費はその月によって使う額が変わるので、変動費に分類されるのよ。
え?スマホ料金も使った分で変わるから変動費?
実際にはプラン次第でどちらにも分類できるし、
家計簿では管理しやすいように便宜上“固定費”に入れることが多いの!
第20問 「高額療養費制度」について正しい説明はどれ?
- A. 月の自己負担が上限額を超えた分が払い戻される
- B. 年間の医療費がすべて0円になる制度
- C. 保険料の支払いが免除される制度
👉 答えを見る
正解:A(上限超過分が払い戻される)
高額療養費制度では、月の自己負担が上限額を超えると超過分が払い戻しされます。

高額療養費制度は、医療費がとても高くなっても、1か月に自分で払うお金には上限が決まっている制度です。
この上限は収入によって違いますが、だいたい 1か月に9万円くらいを目安に考えておけば安心 です。
たとえば入院して医療費が50万円かかっても、実際に支払うのは上限までの金額で済み、それ以上はあとから払い戻されます。
| 年収(目安) | 所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当(過去12ヵ月以内3回以上超えた場合) |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円~ | ア(上位所得者) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 約770万円~1,160万円 | イ(高所得者) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 約370万円~770万円 | ウ(一般) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| ~約370万円 | エ(低所得者) | 57,600円 | 44,400円 |
| 非課税世帯 | オ(住民税非課税) | 35,400円 | 24,600円 |
✅ 採点の目安
クイズが終わったら、自分の正解数を数えてみましょう。
下の目安を参考にして、あなたの金融リテラシーレベルをチェックしてみてください。
- 10問中 7問以上正解(70%以上) → 合格!🎊 初級レベルの金融リテラシーはしっかり身についています。
- 10問中 5〜6問正解 → もう一歩!🥉 あと少し復習すれば合格ラインに届きます。苦手な部分を確認してみましょう。
- 10問中 4問以下 → 再チャレンジ!😢 最初は1問も解らなくても全然へいき!これから知識(武器と盾)を身につける楽しみがあるね!
🐡の記事が「参考になった🎣」「また読みたい🐟」と思ってくれた方は、
⬇️ポチッと応援よろしくお願いします!🐠
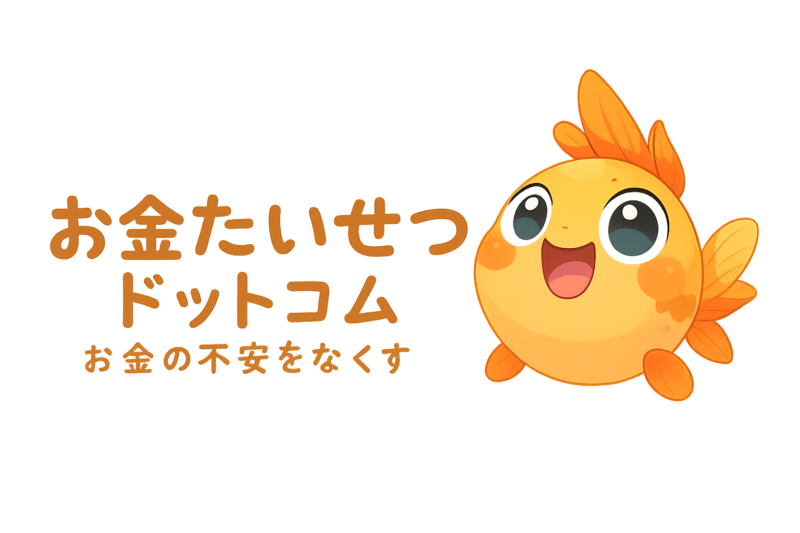
あなたにお薦めな記事
楽しく学べる!金融リテラシークイズ10問|お金の基礎知識をチェック『初級編その①』
楽しく学べる!金融リテラシークイズ10問|お金の基礎知識をチェック『初級編その②』
楽しく学べる!金融リテラシークイズ10問|お金の基礎知識をチェック『初級編その③』
💰楽しく学べる!金融リテラシークイズ10問|お金の基礎知識をチェック『中級編その①』




コメント