
今回は 第21問〜第30問の10問 に挑戦です!
- 金融リテラシー初心者でも楽しく学べる!お金の基礎知識クイズ
- 第21問 給与明細にある「社会保険料」に含まれるものはどれ?
- 第22問 消費税の標準税率は10%ですが、軽減税率が適用される食品の税率は何%でしょうか?
- 第23問 クレジットカードの「一括払い」を利用した場合の手数料は?
- 第24問 夫が亡くなったとき、妻が相続する財産には「配偶者控除」があります。控除額として正しいのはどれ?
- 第25問 国民年金の保険料を免除・猶予してもらった期間は将来の年金額でどう扱われる?
- 第26問 クレジットカードのキャッシング利用にかかる金利は?
- 第27問 NISAやiDeCoのような制度を使う主なメリットは?
- 第28問 株式の配当金にかかる税金(源泉徴収)の税率は?
- 第29問 サラリーマンの妻がパートで働く場合、税金上の「配偶者控除」を受けられる年収の上限は?
- 第30問 物価が上がり続けることを何という?
- 点数結果
- あなたにお薦めな記事
金融リテラシー初心者でも楽しく学べる!お金の基礎知識クイズ
第21問 給与明細にある「社会保険料」に含まれるものはどれ?
- A. 健康保険・厚生年金保険・介護保険
- B. 所得税・住民税
- C. 財形貯蓄
答えを見る👈クリック
正解:A(健康保険・厚生年金保険・介護保険)
給与明細の「社会保険料」には健康保険・厚生年金・介護保険が含まれます(雇用保険は別表示が多い)。

給与明細の「社会保険料」は一般に健康保険・厚生年金・介護保険を指します(雇用保険は別表示が多い)。
第22問 消費税の標準税率は10%ですが、軽減税率が適用される食品の税率は何%でしょうか?
- A. 8%
- B. 10%
- C. 12%
答えを見る👈クリック
正解:A(8%)
標準税率は10%ですが、飲食料品や新聞は軽減税率で8%です。
ただし外食や酒類は対象外で10%のままです。

持ち帰り品は基本8%。店内で食べると10%。お酒は贅沢品なので10%
- 対象になるもの スーパーで買う食料品、飲料水、テイクアウトのお弁当、定期購読の新聞など
- 対象外になるもの レストランや居酒屋などの 外食、アルコール飲料(ビール・日本酒など)
第23問 クレジットカードの「一括払い」を利用した場合の手数料は?
- A. 原則かからない
- B. 年率10%かかる
- C. 月500円かかる
答えを見る👈クリック
正解:A(原則かからない)
クレジットカードの一括払いは手数料ゼロ。分割払いやリボ払いでは利息が発生します。

今の時代、楽天やイオン、三井住友のDポイントのポイ活が定番になってきな!楽天なんて特に、そのポイントで楽天モバイルの料金も払えるからお得!
第24問 夫が亡くなったとき、妻が相続する財産には「配偶者控除」があります。控除額として正しいのはどれ?
- A. 1億6,000万円 または 法定相続分のどちらか多い金額まで非課税
- B. 一律5,000万円まで非課税
- C. 配偶者には一切相続税がかからない
答えを見る👈クリック
正解:A(1億6,000万円 または 法定相続分の多い方まで非課税)
配偶者は特別に大きな非課税枠があり、基礎控除とは別に適用されます。

相続にはまず「基礎控除」があり、妻だけが相続人なら 3,600万円 までは非課税です。
さらに妻には特別に「配偶者控除」があり、1億6,000万円または法定相続分の多い方 まで非課税となります。
この2つを合わせると、妻1人の場合は 最大1億9,600万円まで相続税がかからない 仕組みです。
子供(相続人)は1人600万円まで相続税はかからないっすね。
第25問 国民年金の保険料を免除・猶予してもらった期間は将来の年金額でどう扱われる?
- A. 反映されない
- B. 一部が反映される
- C. 全額が反映される
答えを見る👈クリック
正解:B(一部が反映される)
国民年金の免除期間は種類により一部反映。追納すると満額に近づけられます。
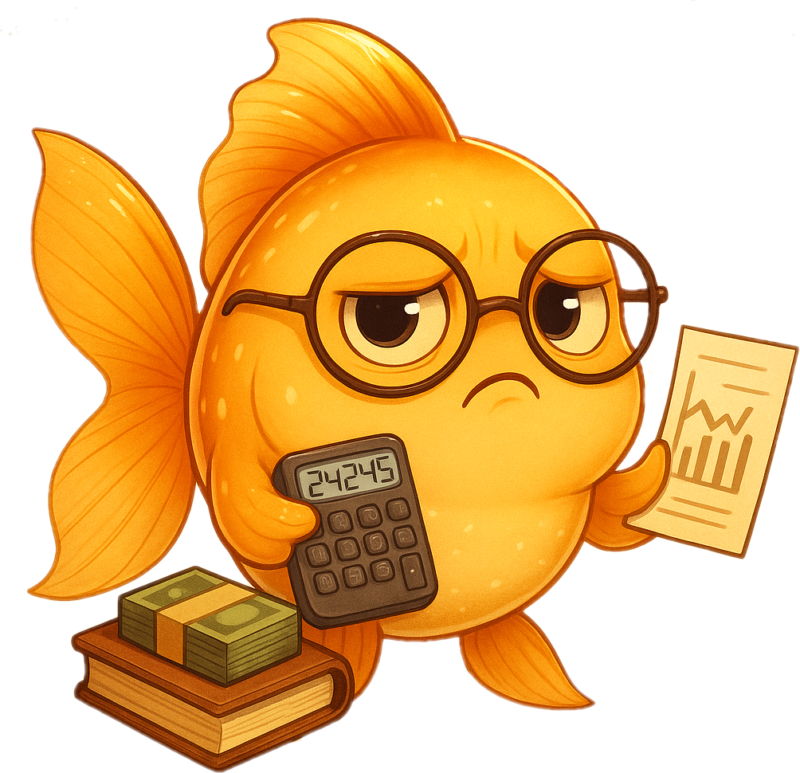
国民年金の保険料を 免除や猶予 してもらった期間は、将来の年金額にどう反映されるかが違います。
- 全額免除 → 将来の年金額に 1/2が反映
- 一部免除(4分の3・半額・4分の1) → 免除の割合に応じて反映
- 猶予 → 将来の年金額には 反映されない(あとで「追納」すれば満額に近づけられる)
第26問 クレジットカードのキャッシング利用にかかる金利は?
- A. 年率15〜18%程度
- B. 年率5%未満
- C. 金利はかからない
答えを見る👈クリック
正解:A(年率15〜18%程度)
キャッシングの金利は高めで、短期利用でも利息が大きくなります。

給料は一年で5%も上がらないのに15〜18%ってほんとアホかと・・
- 10万円を1年間借りたら → 約1万5,000〜1万8,000円の利息
- 30万円なら1年で → 約4万5,000〜5万4,000円の利息
第27問 NISAやiDeCoのような制度を使う主なメリットは?
- A. 税金が優遇される
- B. いつでも現金がもらえる
- C. 利息が必ずつく
答えを見る👈クリック
正解:A(税金が優遇される)
NISAは運用益が非課税、iDeCoは掛金が所得控除など税制メリットがあります。

政府が導入した とてもお得な制度 が話題になっています。
普段は税金でしっかり取られてしまう私たちですが、この制度を使えば 大きな節税メリット を受けられます。
将来のためにぜひ上手に活用しようね!
第28問 株式の配当金にかかる税金(源泉徴収)の税率は?
- A. 約20%(正確には20.315%)
- B. 約10%
- C. 無税
答えを見る👈クリック
正解:A(約20%/正確には20.315%)
内訳は所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%です。

株や投資信託の利益には 本来20%の税金 がかかるんだけど、
実はそこにさらに 0.315%の復興特別所得税 が上乗せされて、合計 20.315% も取られてるんだよね。
「たった0.315%でしょ?」って思うかもしれないけど、これが 2013年から2037年まで25年間ずっと続く。
毎年3,000億〜4,700億円の税収がちゃんと復興に使われているのかしら?
震災から何年経ってると思ってんの!?って、投資家の間では不満の声が多いのよ。
第29問 サラリーマンの妻がパートで働く場合、税金上の「配偶者控除」を受けられる年収の上限は?
- A. 約103万円まで
- B. 約130万円まで
- C. 制限はない
答えを見る👈クリック
正解:A(約103万円まで)
税金上の配偶者控除は年収103万円以下が目安。社会保険の扶養は130万円未満と制度が違います。

103万円の壁は50年以上変わっていません。
物価も時給も上がっているのに、基準は昭和のまま放置。
| 年代 | 平均時給(最低賃金) |
|---|---|
| 約50年前(1975年) | 315円/時 |
| 現在(2024〜2025年) | 約1,055~1,118円/時 |
週20時間働くだけで103万円を超えてしまい、働く意欲にブレーキがかかっています。
「いい加減見直してほしい」という不満が多いのも当然です。
第30問 物価が上がり続けることを何という?
- A. デフレ
- B. スタグフレーション
- C. インフレ
答えを見る👈クリック
正解:C(インフレ)
インフレとは物価が継続的に上がり、貨幣価値が下がる状態です。

うまい棒が10円が懐かしい

みんなが愛するうまい棒も、20円になる日は近いかもしれないっすね!
点数結果
🎯 クイズが終わったら、正解数を数えてみましょう!
下の基準で、あなたの金融リテラシーレベルをチェックしてみてください。
- 10問中 7問以上正解(70%以上) → 🎉 初級合格! おめでとうございます!お金の基礎知識はしっかり身についています。
- 10問中 5〜6問正解 → 😅 もう一歩! 惜しい!あと少しで合格ラインです。苦手な部分を復習しましょう。
- 10問中 4問以下 → 💦 再チャレンジ! 今回は残念!でも大丈夫。記事を読み直して、基礎からもう一度チェックしてみましょう。
🐡の記事が「参考になった🎣」「また読みたい🐟」と思ってくれた方は、
⬇️ポチッと応援よろしくお願いします!🐠
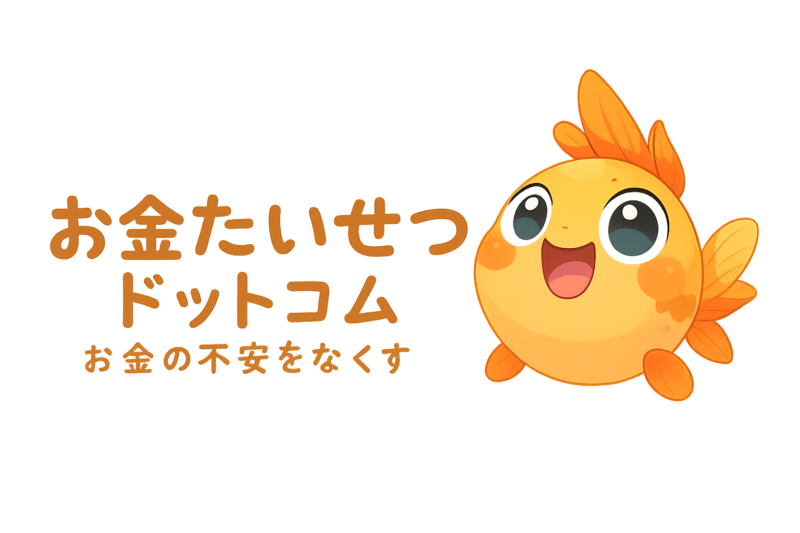
あなたにお薦めな記事
楽しく学べる!金融リテラシークイズ10問|お金の基礎知識をチェック『初級編その①』
楽しく学べる!金融リテラシークイズ10問|お金の基礎知識をチェック『初級編その②』
楽しく学べる!金融リテラシークイズ10問|お金の基礎知識をチェック『初級編その③』
💰楽しく学べる!金融リテラシークイズ10問|お金の基礎知識をチェック『中級編その①』




コメント